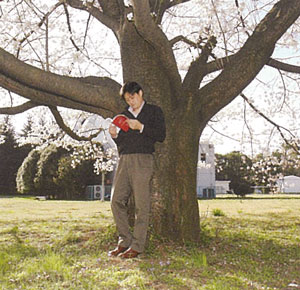
今回は、本間希樹さんの本棚にお邪魔しました。VERAプロジェクトで大きな研究成果をあげつつある本間さん。ご専門の銀河系のダークマター関係の論文から、石垣島を舞台にした小説、幕末ものと幅広いジャンルをカバーした、その本棚の最後に控えていた至宝の1冊とは?
本間 希樹 | Honma Mareki
准教授(水沢 VERA 観測所)
1971 年テキサス州生まれ。専門は銀河天文学、高精度アストロメトリ。ゴーチェ子午環脇の桜の木の下で。手にもつのは「第九」のスコア
大きな影響を受けた論文 その①
――“Possible gravitational microlensing of a star in the large magellanic cloud” (1)
最初に登場するのは、初めて発見された重力マイクロレンズ現象についての論文。マッチョ(MACHOs=Massive Compact Halo Objects)ですね
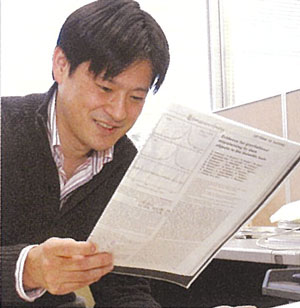 「論文は、まずは速読。図を見て、ふむふむ、って感じです」
「論文は、まずは速読。図を見て、ふむふむ、って感じです」
学部 4 年の時に祖父江先生から薦められた論文の 1 つです。当時ナゾとされていたダークマター問題が、もしかしたら解けたかも !? という論文です。その後、MACHOs だけではダークマター候補として不十分ということが判明したんですが、これをきっかけに私も銀河系の質量に注目してダークマターの研究に参入しました。あれから、早 15 年。相変わらず正体不明のダークマターを追って研究を続けていますが、ちょうど本格的な研究を始める時期に、これほどの大テーマを扱った論文に出会えたのはラッキーだったと思います。
ただ、この論文の強烈な思い出は別にあって、読んだのが忘れもしない1993 年10 月29 日。かつてサッカー少年だった私にとって、それがドーハの悲劇が起こった歴史的アンラッキーな日の翌日だったというのは、やっぱりダークな巡り合わせだったのかもしれませんね(笑)
大きな影響を受けた論文 その②
そして、WMAP の成果ですね
 「論文の引用件数も4400 件。すさまじい。ふつう1000 件でノーベル賞ものですよ
」
「論文の引用件数も4400 件。すさまじい。ふつう1000 件でノーベル賞ものですよ
」
ええ、これ、恐るべき論文なんです。宇宙の年齢やダークマター、ダークエネルギー関連の宇宙論のパラメータを…、誰もが知りたい事をね、一挙に明らかにしちゃったんです。ダークマターやダークエネルギーの正体そのものは、依然として不明なんですが、宇宙モデルの枠組みはこれで決まり。この論文を読んだときは、かなりの衝撃で、正直『負けた、こんなことできるのか~』って思いましたね。アメリカの凄さと、日本との格差をまざまざと見せつけられたショッキングな論文でした
★順めも:現代天文学の最大の謎のひとつダークマター。「もともと銀河系にどれくらいのダークマターがあるのかを知りたくて、銀河の回転や運動を研究する VERA に参加した」という本間さん。「でも、ダークマターの研究は、未だに暗中模索といったところもあって、アプローチの仕方も素粒子的だったり天文学的だったり。だから、できるだけアンテナを張り巡らすように心がけています」。そんな本間さんが、密かに、ダークマターの正体解明の歴史的論文のお手本になるかも、と考えているのが…
大きな影響を受けた論文 その③
――“Molecular structure of nucleic acids” (3)
これはまた、短い論文ですね。
えっ、これでノーベル賞受賞 ?!
はい、あまりにも有名な、ワトソンとクリックの DNA の二重螺旋の論文です。短すぎて驚きでしょう。これ、本当に凄い。何とたったの 1 ページ。これで終わり。しかも、どうです、この手書きっぽいラフな図(爆笑)。でも、この素っ気無い二重螺旋の概念図 1 枚に歴史的大発見のすべてが凝縮されています。まあこれは、たいへん極端な例なんですけど、自然の本質を真に衝いた重要な発見というのは、きっとこういう質のものなのではないか ? と感じられて面白い。こんな痛快無比な論文、一生に一度でいいから書いてみたいですね
★順めも:二重螺旋の概念図。これなら、わたしでも、ラクに描けそう。ちなみに生命科学にも興味があった本間さんでしたが、「血をみると、もうダメ~」というわけで天文学へ、とのこと
思い出の本 その①『夏化粧』
『夏化粧』/池上永一著(文芸春秋 2002)
『やどかりとペットボトル』/池上永一著(河出書房新社 2006)
なにやら、付箋がたくさん
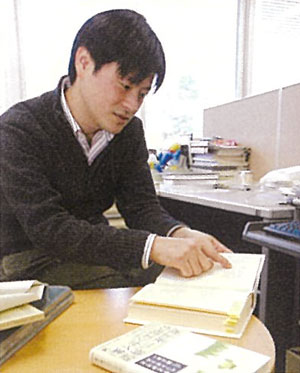
「『やどかりとペットボトル』は、池上さんの著書ということで読みました。抱腹絶倒です」
ええ、VERA の石垣島観測所が登場しているページです。これは、石垣島を舞台にしたファンタジー小説なんです。観測所の所員が出てくるくだりもあって、『運用担当の職員が気さくに話してくれた。最近 VERA は誤動作するんだ』。で、その職員のモデルはどうやら私らしい(笑)。というのは、文春の編集者が大学時代の知り合いで、その関係で池上さんの取材協力をしたんですね。まあ、内容はかなりぶっとんでるんですけど、なんていうかな、これを読むと “島”独特の匂いが甦るというか……。VERA に参加して、石垣島で観測局の立ち上げを一から担当したときの懐かしい思い出がたくさん詰まった一冊ですね
思い出の本 その②『竜馬がゆく』『世に棲む日日』
来ました ! 司馬遼 (4)(5)。幕末維新モノのスタンダード登場 !
司馬遼太郎の本には時々ハマるんです。当時の血気盛んな若者たちが、有り余るエネルギーを世直しのために注ぐ。今のままじゃ、日本はダメになる~ってね。これが実に生き生きと描かれている本で、あー、青春だなあ…と。元気出ますよね。私は母方が下関なので長州びいきなんですが、VERA の一局は薩摩。でも VLBI ネットワークの山口大もパートナーのひとつ。ええ、オチは薩長同盟というわけで(笑)
最近ハマっている本 『私本太平記』
こちらは、グッと時代を遡りましたが
吉川英治 (6)も好きなんですが、じつはこれ、調べものでハマってるんです。2 月に男の子が生まれて、家紋が入った産着を作ることになって親父が家系を調べ たんですね。父方は佐渡なんですが、本間姓を辿ると、どうやらルーツは鎌倉期まで遡る。そこで、くわしく調べてみたら、太平記に出ているとわかったんです。で、吉川版の太平記で、どんな登場の仕方をするのかな~と。ご先祖様、見せ場もあるんですが、出てきたと思ったら、仇討ちの敵役だったり(笑)。歴史物でこんな読み方を体験できるとは思ってもいませんでしたね
『ベートーベン交響曲集、ピアノソナタ集、弦楽四重奏曲集』 (7)

――本棚コーナー初の楽譜が「私の一冊に」! ♪
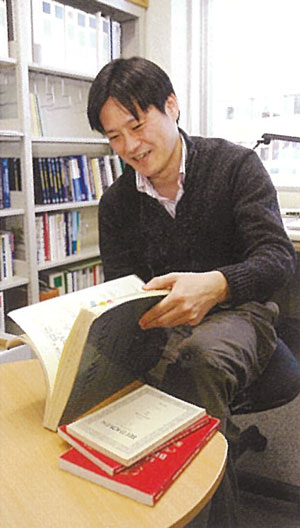 「カミさんがピアノの教師なので、ソナタ集の大判の楽譜を借りて来ました」
「カミさんがピアノの教師なので、ソナタ集の大判の楽譜を借りて来ました」
これしかありません。他にはありません。私の本棚にあるもので、どんな本よりも最も価値あるものです。あとの本は要らないです。人類の至宝! 私の一冊はこれで決まりです
本間さん、熱すぎです
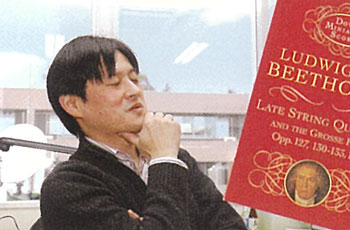 「ベートヴェンの直筆の楽譜は、ラフすぎて写譜職人を困らせたんですよ」
「ベートヴェンの直筆の楽譜は、ラフすぎて写譜職人を困らせたんですよ」
いえ、全然(笑)。私は、サッカー少年だったのですがヴァイオリンもやっていて、大学からその後 10 年くらいは、オケ三昧。で、筋金入りのベートーヴェン・マニアに。いや信者に。彼の音楽は、単純で時にはチープにも聞こえる旋律(の断片 ?)を元に展開されるのですが、その変奏によって切り拓かれる精神世界があまりにも高く深い。このような手法で人の魂を揺さぶる音楽を一つの構造体として設計し、それを実現できる作曲家は彼しかいない。
とくに後期~晩期のピアノ曲は、彼の精神性がとことん突き詰められ、いらない要素を一切そぎ落として、作曲したら、ついにこうなりました! 表向きの美しさはありません。でも、清澄かつ崇高。たった一台のピアノで生み出される音楽が、これほど魂の奥まで染み入る世界を作っていること自体が、この世の奇跡なんですね。この話題なら、何時間でもお話しますよ(笑)

