
●今回お話を伺ったのは、光赤外研究部の青木和光さんです。青木さんは分光学がご専門。恒星内部の元素合成の研究をメインテーマに、すばる望遠鏡の高分散分光器(HDS)の開発・運用から、すばるの広報担当、一般普及書の執筆まで幅広くご活躍中です。そして最近、もうひとつ「さらに忙しくなったけど、新発見の日々!」という新ジャンルも開拓中。「私の一冊」は、その分野のマイ教科書(!?)。では、青木さんの本棚をご紹介します。
青木 和光 | Aoki Wako
助教(光赤外研究部)
1971 年群馬県生まれ。専門は恒星物理学、天体分光学。一般向けの著書に『物質の宇宙史 : ビッグバンから太陽系まで』/新日本出版社 2004(三鷹図書室所蔵)がある
思い出の専門書 その①「壊れゆく教科書」
うわ、これ、ボロボロですね。あっ!
 「このテープ補強、なかなかでしょ」。
「このテープ補強、なかなかでしょ」。
油断すると壊れちゃうんです(笑)。
“The observation and analysis of stellar photospheres”。これ、分光観測の教科書ですね。図が多くて『こういう観測したいな』と思ったときに、要点をつかむのに役立ちます。大学院に入って分光学やろうと思って、人に薦められて読みました。他にもテキストはいろいろ読んできていますが、手元において重宝しているのは、この本ですね
名著なんですね
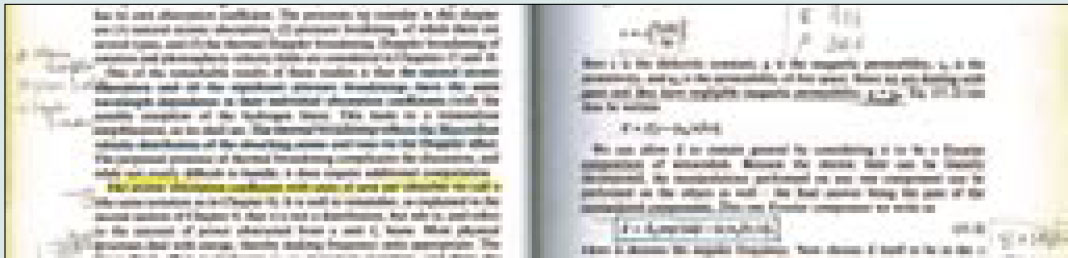 書き込み多数。暗線、輝線だらけです。
書き込み多数。暗線、輝線だらけです。
分光学って、わりと古典的な分野なので、もっと名著はあるのですが(笑)。この本は、観測の実践的な内容がバランスよくまとめられているのがセールスポイントで、名著というよりは “使い甲斐のある” 良書なんですね。こんなにボロボロになったのは、ゼミの学生と何度も開いては議論していたのも一因です。だから “思い出の” じゃなくて、現役ですね
★順めも:恒星の分光観測のスタンダードなテキスト。取材の最中に壊れていくのには、ちょっとハラハラ。1976年に初版、1992年に第2版、そして2005年に第3版と改訂を重ねて、恒星分光学の世界では、息の長い人気を誇るようです。が、「私は、刊行直後にこの第 2 版を買って読み始めたのですが、改訂版のくせに結構間違いがあって……。その後も、ゼミの学生と読んでいて、『ん~、ココ、何でこうなるの?』ということも(笑)。最近第3版が出たので、ちゃんと修正されているか、今度確かめようと思っているんですよ」。とはいえ、表紙に張られた補強テープの年輪に、青木さんの、深い愛着も感じてしまう一冊でした
思い出の専門書 その②「新品同様の名著」
2冊目 は、“Molecular spectra and molecular structure --vol.1 Spectra of diatomic molecules” ですね
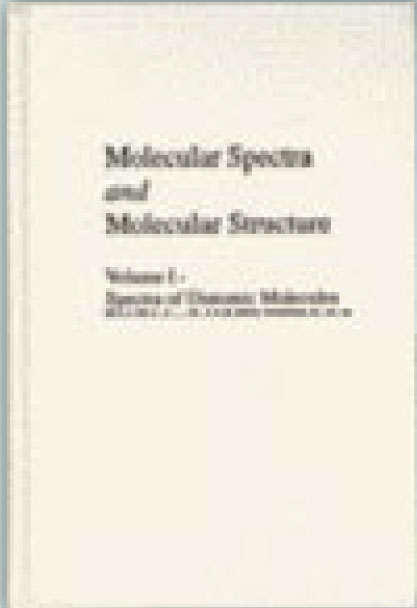
これは分子分光学の教科書です。化学の世界で長く読み継がれている名著ですね。博士課程に進んで、ISO の赤外データを扱うようになって、分子の勉強を本気でやらなきゃ! と自覚したときに出合った本です。もう半世紀以上前の本ですが、体系立てて書いてあるし、表現も分かりやすい。基本はそれほど変わっていないので、今でも一読の価値はあると思います
でも、これピカピカの新品みたいですけど
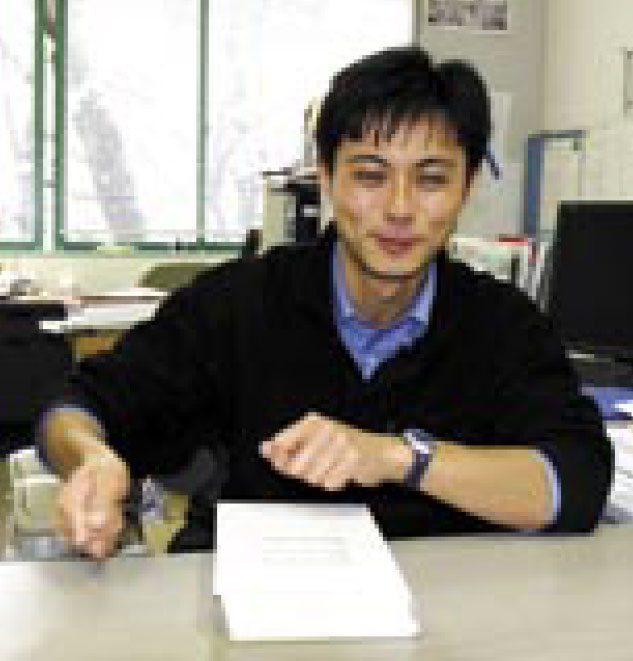 “vol.2 Infrared and Raman spectra of polyatomic molecules” もよく読みました。3、4 はパラパラ程度です
“vol.2 Infrared and Raman spectra of polyatomic molecules” もよく読みました。3、4 はパラパラ程度です
はい、これは最近買ったものです(笑)。実は今まで使っていたものを無くしてしまって。最初、図書室から借りて読んでいたのですが、図書室の本にメモはできないので、必要な個所をその場でせっせと複写して、書き込みをしていったのです。それが昂じて、ついにそれらをまとめて製本し、自分用の教科書として長らく使っていました。それを人に貸しているうちに行方不明になって……、そんなこともあってとても思い出深い本ですね
★順めも:ラジカルな分子の状態や構造を分析するための分光法を解説した 4 巻シリーズ本。著者の Gerhard Herzberg(1904-1999)は、1971 年にノーベル化学賞を受賞。取材前にリストをいただいたときに、「天文学の研究なのに、なんで化学の本が?」と思っていた私ですが、青木さんの説明を聞いて、宇宙は大きな化学実験室で、それを観察する手段が分光学なのだと、ちょっぴり理解できたのでした
思い出の論文「パラパラめくって大発見!」
――おおっ、当コーナー初の論文登場!
“Nucleosynthesis in Asymptotic Giant Branch Stars: Relevance for Galactic Enrichment and Solar System Formation” です (3)
 「論文は電子ジャーナルで読みます」
「論文は電子ジャーナルで読みます」
 「発見は Pb がポイントでした」
「発見は Pb がポイントでした」
大学院生の時は赤色巨星の分光観測していたのですが、国立天文台に就職してから、すばる望遠鏡の高分散分光器(HDS)の開発に取り組みました。それをハワイへ送り出して、ヤレヤレというときに偶然パラパラと読んだ論文のレビューがこれです。赤色巨星の最終段階の元素形成を論じたものなのですが、ピンと来るところがあって、別の目的で細々と解析していた星のデータを調べたら新たな発見があったんです。そのおかけで、著者の Gallino さんとのやりとりが始まったりして、新参者の私が、この業界に一歩足を踏み出すきっかけを作ってくれた、とてもありがたい(笑)論文レビューですね
★順めも:パラパラめくった 1 篇の論文が……“偶然? 必然? 不思議な出会い”にピッタリのお話。この後、青木さんは、HDS を使って恒星表面の組成を調べる研究を続けています。「最近力を入れているのが、最も古い星(宇宙の初代星)を探しだすことですね」と、研究室の壁にはってある核子図を指差してミニレクチャー。でも私は図のカラフルさに惹かれてしまいました。
人生でもっとも大きな影響を受けた本

――そして、一般書も含めた、青木さんの「私の一冊」は『おーい父親』です (4)
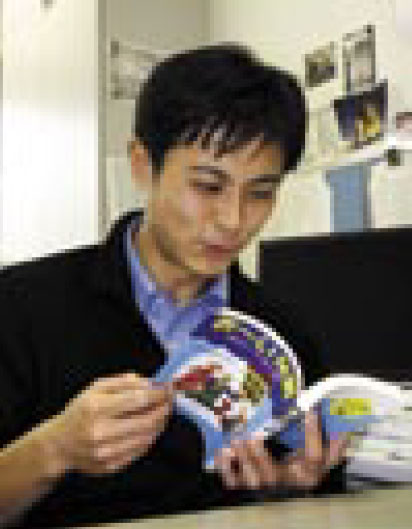 夫婦篇も面白いです
夫婦篇も面白いです
4 年前に男の子が生まれて、その前後に読みました。トピックスが並んだ手軽な読み物です。で、これから心配だなあ、という時だったんですけど、楽しいよーって書いてあるんです。そんなもんかと思って、育児にかかわり始めて、今ハマってます(笑)。ナルホドと思ったのは、育児をする時は他のことは忘れて専念しなさい、それが子どもにとって良いことだ。あれもやらなくちゃ、これもやらなくちゃとイライラ状態でやるのはよくない、と書いてあって、やってみると本当にそう。こちらもスーッと楽しくなっちゃうんです。育児はたいへんですが、新発見の日々。そのとき、この本の内容を思い出すことも少なくありません
★順めも:青木さんの生活感がにじみ出る「私の一冊」です。ちなみに、最近の発見は「最初苦痛だった絵本の読み聞かせが楽しくなって、しかも、よく見ると絵本ってすごく凝って作ってあることにビックリ!」だそうです
他にも、影響を受けた本
科学者の社会的責任を考える絶好の書
『科学者をめざす君たちへ:科学者の責任ある行動とは』 / 米国科学アカデミー編:池内 了訳(化学同人 ,1996)
これは、これから研究者をめざす院生に、とくに読んでもらいたい本ですね。初版は 1990 年代ですが、データの捏造事件や手抜き行為など、日本でも騒がれだした科学者のモラルの問題が、ケーススタディ形式でまとめられています。そして“社会の中の科学”という視点から、自分たちの研究のあり方を見つめなおすきっかけになればいいな、と思います
すべての道はローマに通ず
『ローマ人の物語』全15巻. 塩野七生著(新潮社, 1992-2006)
歴史はもともと好きなのですが、ロー マものならこれ。昨年ようやく完結しましたね。1 年に 1 巻ずつ出る新作を読むのが楽しみでした。欧米の研究者と付き合っていると、ああ、彼らのものの見方には、ローマが色濃く反映しているなあ、と思えることもしばしば。そして科学もヨーロッパが源流。研究者としての自分の立脚点を考える上でも示唆に富むかも。えっ、私が気に入った皇帝? 評判以上にすごいと思うのはアウグストゥス、好きなのはウェスパシアヌスですね(笑)

