川辺 良平 | Kawabe Ryouhei  教授/野辺山宇宙電波観測所所長/野辺山太陽電波観測所所長
教授/野辺山宇宙電波観測所所長/野辺山太陽電波観測所所長
1957年生まれ。三鷹市出身、育ちは伊豆。北海道大学理学部物理学科卒。名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了。東京天文台助手、国立天文台助手、助教授を経て1998年より現職。
専門は電波天文学、特に星・惑星系形成や銀河形成、銀河の活動性など。
天文関係の思い出の本・最近印象に残った本
アウトドアな小学生時代の本
川辺:子どもの頃はあまりじっと家の中にいなくて、晴れていれば外に行って山へアケビを採りに行ったり昆虫を採りに行ったり、友だちとベーゴマや面子をしてました。ところが、雨の日は外に遊びに行けないじゃないですか。そんな時の私の友が『こども科学館』なんです。
私の家では、本は本棚ではなくて押し入れにしまわれていたんで、雨が降ると押し入れから何冊か取り出してきて見る。その中に今でも私の目、頭の中に焼き付いている図があるんです。(写真下)
川辺画伯、ただいま思い出の宇宙の図を描いています
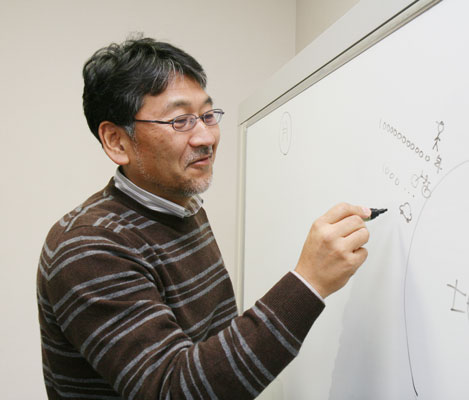
「宇宙も面白いけど、人間も面白いですよね。雑談、とくに飲んで盛り上がると、すごいアイデアが出てくるのはなぜ?(笑)。重要ですよね。若い人に元気がないとよく飲みに連れ出すんですよ。」
川辺:地球から月を見ていて、歩いて行くと100・・・・・年。自転車だと10・・・・・年、自動車、新幹線、ロケット、光という感じで段々と速いものになってきて、「ゼロ」が少しずつ減ってくる。光になると単位が「年」から「秒」になるんです。
「ほほぅ、月まではこんな距離なんだ。こんなに宇宙は広いんだ」って思いました。本がボロボロになるまで何回もなんかいも見てました。小学校高学年の時でしたけど、この時に初めて宇宙を意識して見た図で、最初の宇宙体験でした。私の宝物みたいなものですね。とは言っても、晴れているとそんな感動はすっかり忘れて(笑)、外へ遊びに行っちゃうんだよね。まさに晴遊雨読だね。
磁石にも興味を持っていたんですけど、棒磁石にはNとSがあるでしょう。それが電気の+・-のようにきれいに分かれないのかなぁと思ってね、ノコギリでギコギコギコッと切ってみたんです。でもやっぱりちゃんとNとSになっているんですよね。不思議だなと思って担任の先生に聞いたら「また難しいことを~。中学校へ行ったら習うからそこで聞いてごらんなさい」って言われたナ。
バイブル本『物理学読本』
川辺:中学時代は伊豆に住んでたんですけど、とても夜空がきれいなんです。家の庭にゴロリと寝転がると一面が星。ちょっと浮遊感のような、宇宙に吸い込まれて行く感覚になって「身体が宇宙に浮いている。宇宙の一部なんだ」って思った。
中学校の担任は大学の物理学科を出たてホヤホヤの新米教師だったんだけど、その時に薦められたのが『物理学読本』なんです。
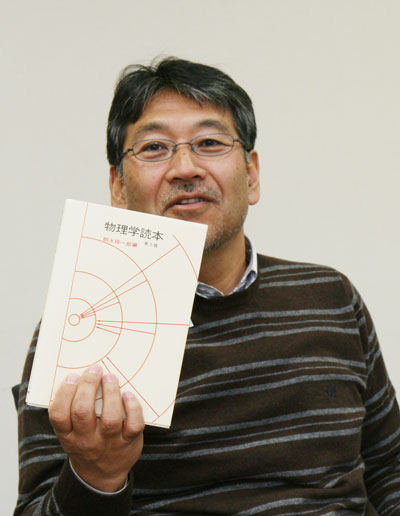 でも伊豆の田舎の書店に置いていなくて、先生に聞いたら新宿の書店にあるっていうからね、伊豆から一人で鈍行に乗って状況したの。帰りの電車の中で本を開いて、まずはきれいな図版にビックリ。中でも、よく覚えているのが、「ヤカン」。氷の上にのって蒸気が出ている図。そこに「氷の上でひとりでに沸騰することはない」って書いてあるんですよ。「こんなの当たり前じゃん!」って思うよね。何でわざわざ書いてるんだろう、物理って変な学問だなぁって不思議に思ったんです。もともとは磁石について知りたかったんですけど、すっかり「ヤカン」に惹きつけられました。
でも伊豆の田舎の書店に置いていなくて、先生に聞いたら新宿の書店にあるっていうからね、伊豆から一人で鈍行に乗って状況したの。帰りの電車の中で本を開いて、まずはきれいな図版にビックリ。中でも、よく覚えているのが、「ヤカン」。氷の上にのって蒸気が出ている図。そこに「氷の上でひとりでに沸騰することはない」って書いてあるんですよ。「こんなの当たり前じゃん!」って思うよね。何でわざわざ書いてるんだろう、物理って変な学問だなぁって不思議に思ったんです。もともとは磁石について知りたかったんですけど、すっかり「ヤカン」に惹きつけられました。
本の構成は、朝永振一郎さんが考えられていて、さすがの一言。これは今読んでも難しいことが書いてあるんだけど、たくさんいい図があるから読んでいてすんなり頭に入ってくる。それに、どんどん知りたいという気持ちが引き出されてきて、物理への関心がふつふつと沸いてくる。とにかく、絶大なインパクトがあって、物理に目覚めたきっかけ本。確かに「ひとりでに沸騰することはない」(笑)
そもそも磁石の原理にもかかわる量子電磁気学っていうのは、朝永さんたちが新たに切り拓いた分野なんですよね。というわけで、この本との運命的な出会いをきっかけに、物理の世界に引き寄せられて、一気に物理という学問に邁進していきました。
今、改めて読み返してみると、こういう身近に転がってる大したことないと一見思える謎も、実は奥深いところで世界の根源的な仕組みにつながっているんだな、と痛感させられますね。
物理オタクから宇宙へ
川辺:その後はすっかり物理オタク。特に量子力学に引き込まれて、高校の図書庫案には2008年にノーベル賞をとった小林誠、益川敏英の先生にあたる坂田昌一さんや武谷三男さんの本もあったりして、けっこう難しい物理の本でもほとんど読んでいました。ブルーバックスも買い漁っていたなぁ。大学も何も悩まず当然の如く、物理学科に進みました。宇宙の方に引き込まれたのは『宇宙創成はじめの三分間』との出合いが一つのきっかけなんです。大学3年の時に将来の自分の専門を決めるにあたって少し悩んでいたんですけど、この頃はちょうどビッグバン宇宙とか宇宙での元素合成とか初期宇宙の様子などが議論できるようになってきていたんです。著者のワインバーグは素粒子物理学の大家で、物理の手法を使って宇宙を解き明かすんですけど、物理の言葉で宇宙を語れる、記述できるというのは、とても面白いと思いました。そして、宇宙には、ビッコウバンの化石というか指紋が残っていて、それを観測すると、宇宙誕生の様子がわかっちゃうと。すげーなー、と。で、大学院では宇宙背景放射を観測してみたいなって思ったんですけど…、実際は全く違うことを研究してました(笑)。
最近、宇宙の観測分野に新規参入してきた私より少し若い先生が、宇宙背景放射の観測をやろうとしているんです。当時私がやろうと思っていたテーマでもあるし、電波天文学の先輩として裏方で後押しをする形でサポートしているんだけど、何だかワクワクするよね。時が巡って、宇宙物理の最初の憧れのテーマに再会すると、とても元気になります。野望再沸騰(笑)。うん、研究者は野望がなくなったら終わりだと思います。
国際協力と競争の世界
川辺:で、研究者の野望実現のための一側面として面白いのが、研究のマネジメントの問題。外国での科学政策や科学研究はどのように行われているかについて元々興味はったし、科学の読み物は好きで昔から読んでいました。野辺山で助手をしていた頃は周りにもお手本になる人達が多くてね、その影響で自分が支えて引っ張っていかなきゃという意識を非常に強く持っていました。必要なものは全部自分たちで作っちゃうっていう「野辺山イズム」というのがあるんですけど、望遠鏡も観測機器も全部作っちゃうんですね。それを発展させて応用する技術は100%完全に理解して自分のものにしないといけない。そのためには、やはり自分も成長していかなきゃいけないし、世界を見て、研究の最前線と全体像をよく理解しないといけない。
具体的なきっかけはやっぱりALMAかなぁ。日本という一国だけではなくて、国際協力で世界の研究者と渡り合っていくんですが、『ノーベル賞を獲った男』は、成功するには何をするべきか、どうするべきか等といった研究ビジネスモデルの一例を知るには最適な本です。タイトルから刺激的ですよね、【獲】って獲得の【獲】の字でしょう。見ただけでクラクラ~っとする(笑)。モデルのカルロ・ルビアはタイトルの通りノーベル賞を獲った男で、素粒子物理学の最前線にいる人なんですけど、すっごく野心家で元気な人です。私もこうなりたいと読み進めながら、改めて意欲をかき立てられたりもしますが、ルビアには参りました。彼のパワフルさ、見習いたいですね。それにしても、学術の@ためにこれだけやるんだよね、っていう…。野心的なプロジェクトを進めるためにはそれだけユニークな人たちがいて、ルビアの素粒子実験になればすっごい人数。そういう人たちをまとめるためにはやっぱりマネジメントもできないといけないし、研究でもすごい努力をする。これには私とても共感しました。
『常温核融合スキャンダル』も、内幕ものでスリリングなんですが、2冊とも人や金といった研究に必要なものを地道に且つ戦略的に獲得していく方法、科学競争や論争の背景、予算獲得の実像などについても実に赤裸々に書かれているんです。何れもガリー・トーブス(著)なんだけど、私は特別好きなんです。テーマを深く咀嚼して、かつ物語としてすごく読ませます。内容も非常に勉強にもなったし、とにかく惹きつけられた本です。
これまでの人生で、大きな影響を受けた書籍
心の故郷・伊豆
川辺:中学校の時から書名をよく耳にしていたのが『しろばんば』『北の海』『夏草冬濤』『あすなろ物語』などなどの井上靖の作品群。井上靖は小学校、中学校は伊豆にいて、その時のことを自伝的に書いているんです。伊豆の描写も多くて、実際に私が子どものころに駆け巡っていたとても具体的でリアルな情景描写もあって親しみが沸くんですよ。シリーズ本は大学生の時に読みました。当時は北海道にいたから余計に懐かしさが込み上げてきて何回も何回も繰り返し読んでいました。
私はあまり出来のいい方じゃないから(笑)苦労しながらきているんです。結構、子どもの時から、これじゃいけない、変わらなきゃ、みたいな悩み多き青春(笑)。毎年、正月早々、伊豆の実家の裏山を登って「こんなグダグダした生活をしていてはダメだ。断ち切って新しい人生を踏み出す」って反省するんです。自分なりの儀式というか気持ちにひと区切りつけて重いを新たにするぞと思うわけですね。とはいえ、現実は‥‥なかなかね。理想は描いていても、常に障害を立ちふさがったりして要領よく行った試しがない。で、そんな儀式がだんだんとエスカレートしてきて、山登りや沢登りもチャレンジして、一種の修行のように、自分の限界を見極めたいと思ってくる。辛ければ辛いほど立ち向かう感じかな。井上靖も同じでね、成長したいんだけど、なかなか成長できないもどかしさがあって、いい方向へ行かなくて、あっちへ行ったり、こっちへ行ったり。葛藤しながら自分探しをするというところ、すごく私の生き方と通じるところがあってシンクロしますね。故郷の裏山で海を見ながら抱いた、あの少し苦い思い以来、ずっと一緒に人生を歩んできた大切な心の友なんです、彼の小説の主人公たちは…。
私の家系は職人・エンジニアが多くて、子どもの時から「手に職を」と言われ続けていたので、根はきっと職人気質なんでしょうね。だから、自分の手で、納得するまでやらないと次に進めない、といった感じはあります。その点、野辺山の水はあっていたし、そこで育まれた成果が、今ALMAにつながっている。それを思うと、やっぱり自分の得意なところで仕事をしていくのがいいのかなあって。最近になって自分の役どころが見えてきた感があるんです。未開拓の地に乗り込んで耕すスロンディア的な役目で、次の世代へ思いを引き継ぐ。こういうの好きなんだけど、皆ついてきてくれないと…ひいちゃったら困る(苦笑)。

究極!宇宙の曼荼羅
川辺:研究も、ひとまわりして原点回帰というか、物理の切り口から天文の世界を描きたいという理想の実現に向けて、新しい仕事を始めたいと思っているんですよ。たとえば、天文学者が観測で理解した宇宙というものを、自分の身体に沁み込んでいる物理の基本を用いて描き直して、究極の世界像を曼荼羅で表すとか、どう?(笑)。
“あすなろ職人”の夢は、宇宙を含めた世界全体のしくみを理解するための術を、自分が納得いくまで作りこんでみたい、ということなんですね。

